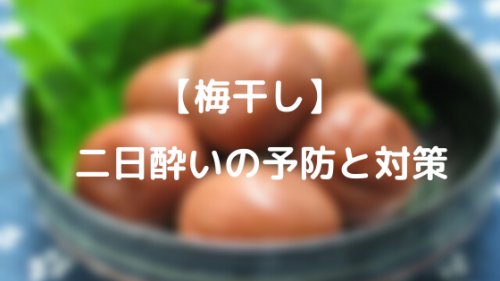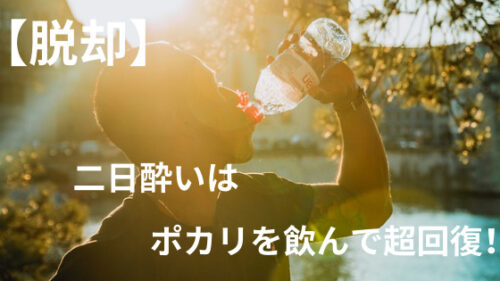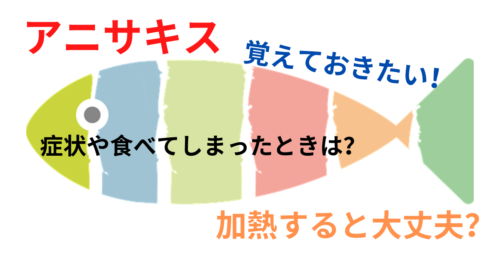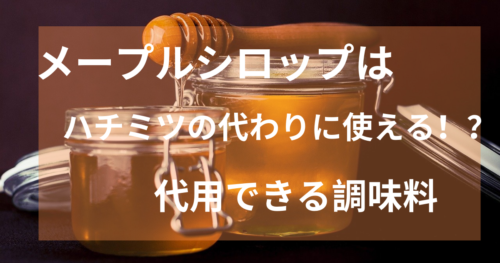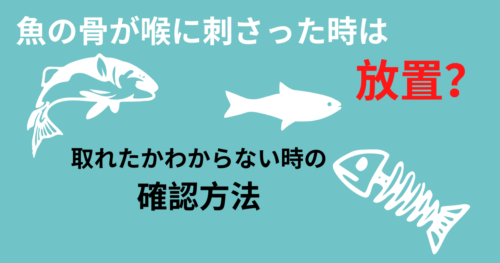うま味成分とはよく耳にしたことがあると思いますが、うま味成分について知っている人って少ないと思います。(知らんけどw)
料理の美味しさに直結するうま味成分。
なんとなく気になって調べていると「相乗効果・対比効果・抑制効果・変調効果」見たこと、聞いたことあるような単語がいっぱい出てきて結構おもしろかったので、今回記事に書き留めることにしました。
うま味=美味しいわけではない
そもそも美味しいとは、味だけではなく食感や匂い、その場の雰囲気や見た目など、人の五感で感じて思うことなんだそうです。
- 味覚ー味
- 嗅覚ー香り・コク・厚み
- 触覚ー歯ごたえ・舌触り・湿度
- 視覚ー色・光沢・形状
- 聴覚ー音(そしゃく音)
これらを感覚機能である「五感」で感じ、美味しいと認識しているのです。
そして今回のお題である「うま味」は五感の1つである”味覚”を基本味に分けた5つの内の1つのことなんです。
 龍之介
龍之介ここら辺りが結構ややこしいんです(笑)
5つの基本味(きほんあじ)とは
5つの基本味とは独立した味を指す公式の呼び名。
「甘味、酸味、塩味、苦味、うま味」これら5つの基本味は、どの味を組み合わせても作り出せない味になっているのです。



この5つの基本味は身体にとっても重要な役割があるそうで
| 代表的な食材 | 体への役割 | |
|---|---|---|
| 甘味 | 砂糖、はちみつ | エネルギー源が体に入るお知らせ |
| 酸味 | レモン、酢 | 腐ったものを食べないようするお知らせ |
| 塩味 | 塩 | 体に必要なミネラル |
| 苦味 | コーヒー、ゴーヤ | 体に良くないものが入らないようにお知らせ |
| うま味 | トマト、かつお節、しいたけ | 唾液、消化液 |



またこれらを五味とも呼ぶそうですが、基本味の中に辛味・渋味も含まれるそうで・・・



五味ちゃうやん!!っとツッコミを入れたのは内緒でお願いします(苦笑)
ではうま味とは何なのか?



うま味とは「深いコクとまろやかさ」がうま味の代表的な味わいだそうです。
何となくわかるようなわからないような感じですが、例えるなら昆布だしの味。
あの深いコクとまろやかさこそが、うま味の味わいだそうで、あの味わいを生み出しているのが「グルタミン酸。」



アミノ酸の一種です。
うま味を感じるアミノ酸はグルタミン酸以外にもたくさんあります。
代表的なのは「グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸」



なんとなく聞き覚えありませんw?



こういった、うま味を感じるアミノ酸を大きくまとめて「うま味成分」とも言われてたりします。



この言い方なら聞いたことある人多いんじゃないでしょうか?
この食材にはうま味成分がたっぷり含まれているので~
うま味成分のアミノ酸とは?
うま味を感じるアミノ酸の代表的なものはグルタミン酸・イノシン酸・グアニル酸。
- グルタミン酸は昆布や野菜など。
- イノシン酸は魚類や肉類に。
- グアニル酸はきのこ類に。



なんとなくお分かりいただけると思います。
あくまでも、これは代表的なことで、うま味成分はほとんどの食材に含まれています。
- コハク酸
- アスパラギン酸
- トリコロミン酸
- イボテン酸
コハク酸は貝類に含まれていて、アスパラギン酸は大豆食品やカツオ節に、トリコロミン酸は食用ハエトリシメジ?に含まれているそうで、イボテン酸は毒キノコに含まれているようです。



毒キノコにうま味成分があるとは驚きです。



そして食用ハエトリシメジとは何なんでしょうか(笑)?



もう、うま味でお腹いっぱいなので次に移行します(苦笑)
初めてうま味を知るのは母乳?
母乳にはグルタミン酸が豊富に含まれているそうで、産まれたばかりの赤ちゃんはうま味を識別できるみたいです(驚)
味覚は、身体に必要な栄養素を取り込むシグナルの役割をしていて、うま味や甘味は心地よい味だそうです。



赤ちゃんって凄いですね!てか人間って凄い(笑)



うま味を産まれたばかりから知るなんて(汗)
少し前(自分の子供が産まれた時)”母乳ってどんな味がするんだろう?”と思い飲んだ事がありますが・・・



普通に不味かったんですけど(赤裸々に告白w)
もちろんコップに移してからですよ(大声)
変な意味じゃないです(真顔)



話しが逸れましたが・・・
うま味成分は組み合わせる事で、さらなるうま味に変わるそうで、このことを「相乗効果」と言います。
うま味の組み合わせは相乗効果だけじゃなく「対比効果」「抑制効果」「変調効果」など食品には組み合わせることによって様々な効果が期待でき、うま味を飛躍的に強くできるのです。



うま味って奥が深いんです。



なんか難しく聞こえるかもしれませんが、次の例を見てみると以外にも腑に落ちる部分が多いんですよ。
相乗効果(そうじょうこうか)とは
相乗効果とは同じ味の食品を組み合わせる事によって更なる旨味を引き出す事。
「グルタミン酸の食品+イノシン酸の食品」または「グルタミン酸の食品+グアニル酸の食品」



これらを組み合わせる事により、相乗効果を発揮しうま味が強く引き出されます。
- グルタミン酸は昆布や野菜など。
- イノシン酸は魚類や肉類に。
- グアニル酸はきのこ類に。



メジャーな相乗効果を出しているのがお味噌ですね。
お味噌のパッケージに「昆布とカツオの合わせだし」とか見たことありません?
昆布(グルタミン酸)とカツオ節(イノシン酸)を合わせているので相乗効果を発揮。うま味を強く引き出しているんですよね。



相乗効果でどれだけうま味が強くなるのかと言うと、単独と比べ約10倍以上にもなると言われています。
対比効果(たいひこうか)とは
2種類以上の異なる味を混合した時に、片方もしくは両方の味を強められること。



片方の味が弱い時に起こりうる効果なんです。
1番わかりやすい例は「スイカ+塩」ですね。
甘いスイカに塩を振りかける事によってスイカの甘みが強く感じられますよね?



これが「対比効果」
それと塩スイーツなんかもそうです。甘味を強くするために塩を入れて対比効果を得ています。



甘味+塩味の場合だけではありません。
お味噌汁やスープ系の時なんかそうですが、何か物足りない時、少し塩を入れると味が上手くまとまってくれる事ってありません?
もしくは、料理の仕上げに塩ひとつまみ入れるとか・・・これも対比効果なんです。



うま味+塩味で対比効果が出来上がります。



他にもまだまだありますが、続いて抑制効果にいきましょ~
抑制効果(よくせいこうか)とは
2種類以上の異なる味を混合した時に片方もしくは両方の味を弱められる効果。



簡単に言えば対比効果の逆ですね。
コーヒーに砂糖を入れて苦味を弱める。これが抑制効果です。



塩焼きした魚にレモンをかけるのも抑制効果です。塩味+酸味で塩味をまろやかにしているので。



そして驚いたのが醤油も抑制効果を用いて作られているんですよ(驚)
醤油は抑制効果が働いているおかげで、醤油はそのまま食べても美味しいんだとか。
醤油には約16%の塩分が含まれていて、その塩分量は口に入れるとしょっぱすぎて吐き出すレベルなんだそう。
でも醤油に含まれているアミノ酸や乳酸などの成分が、抑制効果を用いているので塩分がまろやかになり、美味しく頂けるようになっているそうです。



抑制効果は凄い(笑)
変調効果(へんちょうこうか)とは
異なる2種類の味を続けて味わった時、後で食べた味が変わる効果。
食塩水を飲んだ後に水を飲むと甘く感じることやスルメやタラコを食べた後にみかんを食べると苦く感じるようなことです。



テレビでミラクルフルーツを食べた後にレモンを食べると甘く感じる!みたいなやつを見た記憶がありますが、これも変調効果だったんですね。
味覚の組み合わせ。うま味成分について語る!相乗効果・対比効果・抑制効果・変調効果まとめ
以上がざっくりとですが「味覚の組み合わせ。うま味成分について語る!相乗効果・対比効果・抑制効果・変調効果」になります。



うま味ってなんだ?
そんなことが気になって調べていくうちに、踏み込んじゃいけない領域に入ったみたいで頭がパンクしそうになりました(笑)



深すぎる・・・w
(けど面白いな~)なんて思ったので記事にしてみました(笑)
できる限り分かりやすいように書いてみたんですが、いかがだったでしょうかw?
まあね、味覚の組み合わせとか、うま味成分を語るには少なすぎる情報量なんで完璧とは程遠い内容ですが。
でも自分みたいに「うま味ってなんだ?」とか「味覚の組み合わせって?」など思ったときにはペラペラっと読める内容にはなっているんじゃないかな?とも思っています。
味覚の組み合わせ「相乗効果、対比効果、抑制効果、変調効果」なんかは覚えておくと料理の隠し味のカラクリが分かって面白いかもしれませんね。
自分が料理する上では、特に相乗効果や対比効果なんかは覚えておきたいところです!



この料理にコレを混ぜるとさらに美味しくなる!とか。
それぞれの人に食べ方がありますが、美味しく感じられるなら、この味覚の組み合わせが働いているのかもしれませんね!