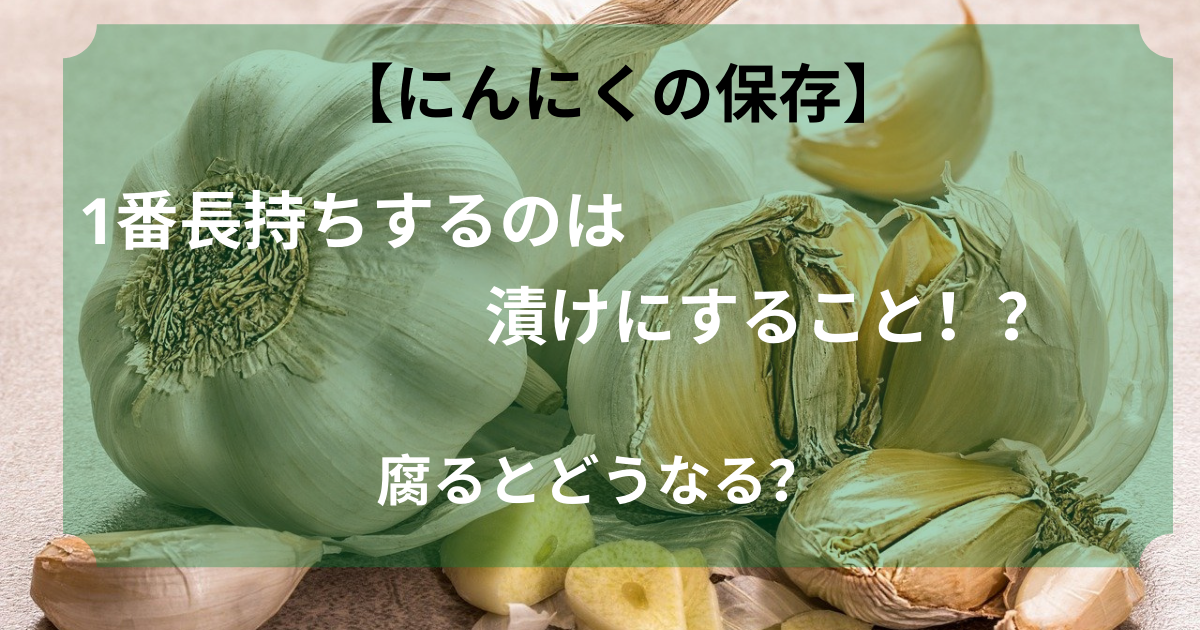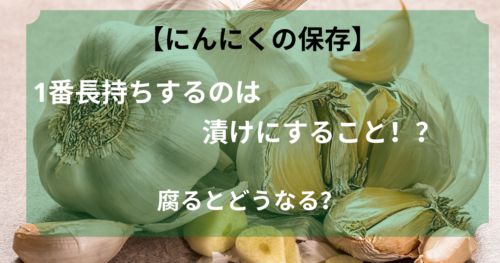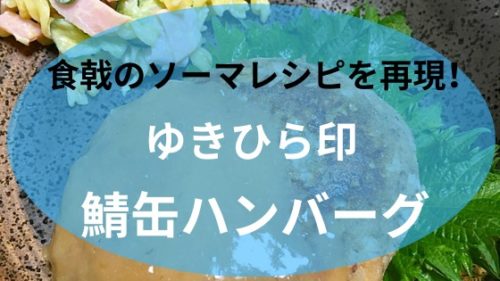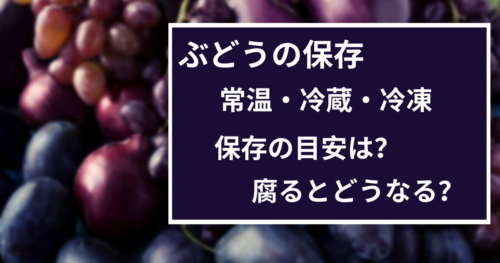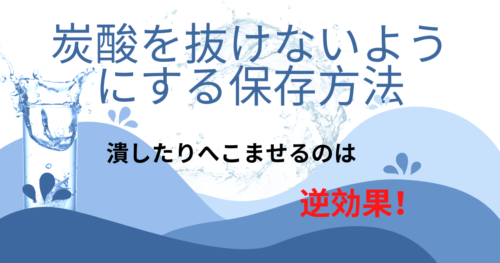今回はにんにくの保存についてお話ししていきたいと思います。
常温保存だったり冷蔵だったりと色々な保存方法がある中で具体的な保存期間をまとめてみたり、長期保存が可能になるにんにくの漬けについてなんかもお話ししています。
- にんにくが発芽した状態とは?
- にんにくの各保存期間
- 醤油漬けの作り方
- 漬けを作る時に使う容器
 まかない君
まかない君などなど。8割ほどにんにく漬け愛が占めている記事内容になりつつありますがどうぞご覧ください。
にんにくの保存の絶対条件
まず、ニンニクを保存する上で絶対条件があり「発芽させない事」なんです。
ニンニクは日当たりが良くて、20度ぐらいの温度、多少の湿気があると簡単に発芽してしまうんです。
時期的に9月~11月は発芽しやすい時期で常温保存している場合は特に注意が必要です。
冷蔵保存や冷凍保存なら問題ありません。0度以下なら芽は出にくくなりますので。
すぐに使う予定があるなら常温で保存する方もいると思いますのでご注意を。
発芽してしまったら芽に栄養が取られスカスカになったり食感が悪くなってしまいます。
決して食べられなくなる訳ではなく、保存するなら発芽しないように。との事です。
にんにくの常温保存



目安の保存期間:1週間
にんにくをすぐに使う予定がある場合は常温保存でも全然問題ないです。
通気性の良いネットやカゴに入れ湿気の少ない冷暗所で保存。
ただし気温が高い時期などは発芽しやすいので、出来れば冷蔵保存がオススメです。



気が付いたら芽が~なんて事良くあるので(自分の中ではw)
にんにくの冷蔵保存



目安の保存期間:1~2ヶ月
一番簡単なのは冷蔵庫での保存です。
そのまんま保存するのではなく、新聞紙や雑誌などのコーティングされていない紙で包んで保存。
冷蔵庫にチルド室がある場合はチルド室で保存するのが良く、無い場合は極力温度変化の少ない場所が好ましいです。
紙等が無い場合は、キッチンペーパーを少し湿らせてからニンニクを包んでも大丈夫。
めんどくさがってビニール袋に包んで保存なんてしないでくださいね。
保存性が落ちる原因になりますので。
にんにくの冷凍保存



目安の保存期間:3ヶ月
ただ冷凍保存場合、にんにくの皮を剥いでからの保存になります。
さすがにそのまんま保存とゆう訳にはいきません(笑)
にんにくの皮と薄皮を剥いでからタッパーやジップロックに入れて冷凍保存。
これだけです。
冷凍のまま刻んだり、すりおろしたりして使えるので長期保存するなら冷凍での保存が便利です。
注意してほしいのは、冷凍のままだと固いですから刻んだり、すりおろしたりする場合は怪我に十分注意してくださいね。
すりおろししてから冷凍保存する場合は?



目安の保存期間:2か月
にんにくをすりおろしてから冷凍保存する事で長期保存、調理時間の短縮にもなります。
保存の仕方は簡単で、にんにくをすりおろしてからジップロックに入れて冷凍保存。
この時、板状に薄く伸ばし上からお箸などで割れ目を入れ冷凍保存します。
こうする事で使いたい時、使う分だけパキっと冷凍のまま簡単に割る事ができちゃいます。
生のまま使う時は自然解凍で。
火を使う時は解凍する必要ありません。
にんにくを漬けにする
にんにくを醤油漬けにしてしまえば保存期間が約1年になります。
にんにくは調味料として保存すると長期保存が可能になるんですよね。にんにくを漬けにすると言っても色々種類があります。
- 醤油漬け
- オリーブオイル漬け
- 味噌漬け
- 酢漬け
- 蜂蜜漬け
- 塩漬け
代表的なものは上記の6種類でその中でも1番ポピュラーなのはオリーブオイル漬けと醤油漬けですよね。
にんにくのオリーブオイル漬けだと、洋風料理などには欠かせない調味料に変化しますし血液がサラサラになる効果を高める働きがあります。
にんにくの醤油漬けはそのまま食べたら絶品おつまみにもなるし万能調味料として活躍する事間違いなしです!
なので今回はよく使えるであろうにんにくの醬油漬けの作り方を記載しておきますね。
にんにくの醤油漬けに用意するもの
- にんにく
- 醤油
- 密封できるビン容器



この3つがあればにんにく醬油が作れます。



ここで注目してほしいのが密封できるビン容器です。
にんにく醬油を入れておく容器はプラスチック製でもいいんですがにおい移りが凄いです。全然取れません。
なのでビン容器がオススメ。におい移りがしないのと、ビン製はよく冷えるので良いです。
あとはフタにゴムパッキンが付いているものがいいですね。
冷蔵庫内でにおい漏れ防止にゴムパッキンは欠かせません(苦笑)



ウチはこの密封ビンを使ってます。
ちゃんとしたゴムパッキンが付いているし、におい漏れをしたことがありません。それにコスパ良しです!
密封ビン容器は煮沸消毒しておく
にんにく醬油は保存期間が1年もありますから保存する容器は煮沸消毒して中を無菌状態にしてから使用するようにしましょう!
煮沸消毒とは、80℃以上のお湯に10分以上浸けることを言います。
鍋に密封ビン(ゴムパッキンも)がしっかりと浸かるくらいの水を入れて火にかけ、沸騰させます。
沸騰後10分以上そのままぐらぐらと煮て、自然乾燥させれば煮沸消毒完了です。



洗剤で洗うだけで済ませたり、自然乾燥を待てなく水滴を拭き取ってしまっては無菌状態にはなりませんからこの準備はしっかりとしておきましょう!



言うまでもなく自然乾燥させる時は逆さまにして乾燥しましょう!
にんにく醬油の作り方
最初はにんにくの下部を皮付きのまま切ります。


ボールに水を溜めて、水の中でにんにくの皮を剥いていきます。
始めは切った下の箇所から剥いていき、途中からは先端を折るように剥いていく。
流水で流しながら剥いていくよりこっちのほうが個人的に剥きやすいです。




皮を剥き終えたらキッチンペーパーなどでしっかりと水気を切ります。
水の中でにんにくの皮を剥くと「手ににんにくのにおいが付きにくくなる」「薄皮まで綺麗に剥ける」嬉しい利点があります。
それにかなりの時短になるのでこの剥き方は本当にオススメですよ。


煮沸消毒した密封できるビン容器ににんにくを入れて醤油を入れるだけです。
基本的に、にんにく醬油を作る時は入れるのは”醬油のみ”です。ほかの調味料とかは一切入れません。



冷蔵庫での保存を忘れずに!
生のにんにくを使っているので味が染み込むのに1ヶ月はかかります。
にんにく量とか醬油の量も適当で、完全好みで入れちゃってください。
賞味期限以内なら醬油が無くなれば足しても全然大丈夫ですよ。ちなみにんにく醬油の賞味期限は1年です。
時短して作る場合
にんにく醬油を作るのに1ヶ月も待てない!



一応にんにく醬油を時短して作る方法はあります。
皮を剥く前に
- 電子レンジでにんにくをラップ無しで1分ほど加熱
- お湯で湯通しする
このどちらかの方法でにんにくに熱を通すと醬油が染み込む時間が2週間ほどになり時短になります。



ただこの作り方は、にんにくに熱を通すので保存期間が縮まるデメリットもあります。なので長期保存を予定しているなら加熱せずに作ることをおすすめします。
にんにく醤油は腐るのか?
基本的に、にんにく醤油が腐る事はありません。
醤油自体に殺菌効果があるみたいでにんにく醬油が腐る事はないようです。



ただ、腐らないと言っても酸化したりすると 風味が落ちたり色が濃くなったりします。賞味期限は1年を目安に。
にんにくの保存!1番長持ちするのは醤油漬け!腐るとどうなる?まとめ
今回はにんにくの保存についてお話しさせていただきました。
その中でも漬けは保存期間が1年と長く、調味料としても凄く重宝できるので強くオススメします。
ご紹介したにんにく醤油漬けなら醤油ににんにくが染みているのでにんにく風味の自家製醤油の出来上がり。
賞味期限(冷蔵1年以内)なら何度でも醤油を継ぎ足すことで無限ににんにく醤油を作ることができます。
酒の肴としては醤油に漬けたにんにくを素揚げにしても美味いですよ!