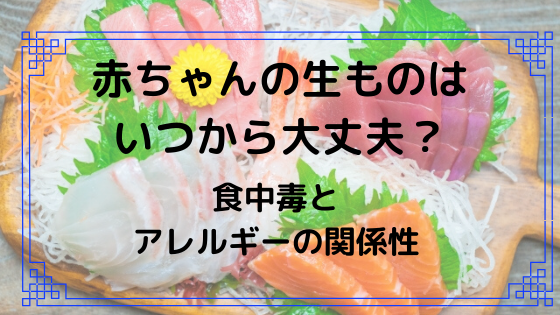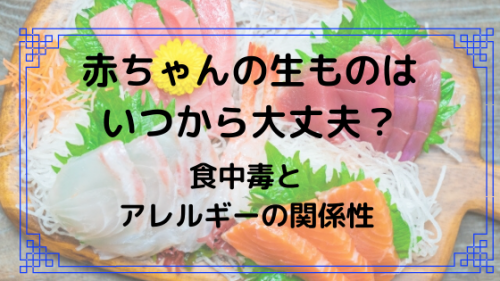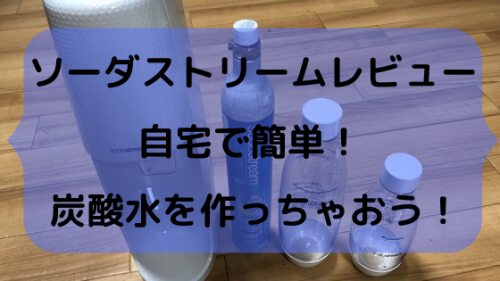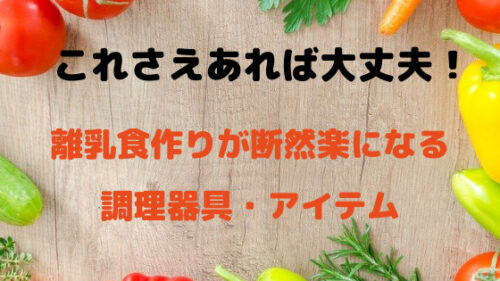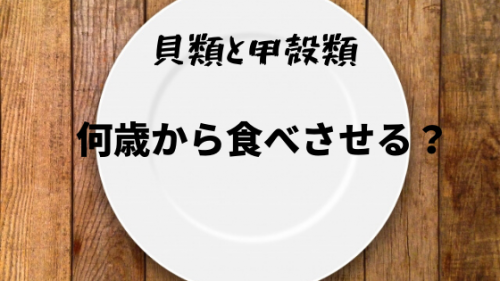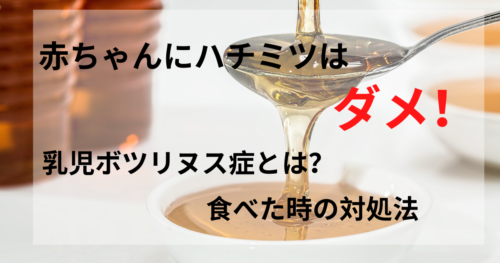赤ちゃんを持つ親にとって、離乳食を完了し普通の食事に変わる時に悩むのがこれではないでしょうか。
普通の食事って?
大人と同じでもいいいの?
ダメな食べ物ってなに?
お寿司とかは食べてもいいの?
 まかない君
まかない君という疑問が生まれる時期です。



僕も結構悩みましたね。
そこで、今回はお刺身や生卵はいつぐらいから食べさせてもいいのか、危険はあるのか、などを詳しくご紹介していきます。
ママやパパがしっかりと理解していれば、赤ちゃんとの食事がもっと楽しくなりますね。
お刺身はいつから?
家族で外食をするときに、回転寿司に行くご家庭がとても多いですよね。
お寿司を食べに行っても、生ものを食べられない子がいると、なんとなくかわいそうで「早く食べられるようにならないかなぁ」と思いますよね。
しかし、赤ちゃんにとってはやっぱり生物はリスクが大きく、気を付けなくてはいけないのです。
赤ちゃんに生ものを与えられる基準として、多くの専門家が推奨する年齢は2歳半くらいとされています。
しかし、専門家のなかには生ものを食べ始める年齢はなるべく遅い方がいいと言う人もいるので、2歳半になったからといって「すぐに食べさせなければいけない」などと言うわけではありません。
赤ちゃんが生物を食べられない理由が大きく分けて3つあります。
- 消化機能が未熟でお腹を壊す恐れがある
- 食中毒の危険性
- アレルギーの心配
1,消化機能が未熟でお腹を壊す恐れがある
消化機能が完全になるのは”10歳”くらいといわれています。
ただ、10歳までお刺身を食べられないというわけではなく、それまでは慎重に食べさせなければいけないということです。
赤ちゃんはまだ歯も生え揃ってはいないため、弾力のある生のお魚を口の中で噛み砕くのは困難で、結局は丸飲みのようになってしまいます。
丸飲みされたお刺身をは、消化機能が未熟な赤ちゃんのお腹ではもちろん消化できないので、お腹を壊してしまいやすいのです。
2,食中毒の危険性
生魚には、細菌や寄生虫が潜んでいる可能性があります。
健康な大人ならば平気な細菌も、免疫力が未熟な赤ちゃんの場合は食中毒を起こしてしまう可能性が高くなります。
さらに、アニサキスなどの寄生虫による食中毒は、大人であってもつらい症状を引き起こします。
赤ちゃんの場合は重症化しやすく、危険ですので特に注意しなければなりません。
アニサキスは青魚に多く寄生しており、サバ、アジ、いわし、かつおなどは食べさせないようにしましょう。
青魚のお刺身が食べられるようになるのは、12歳くらいですが、それでもなるべく遅ければ遅い方がいいという専門家もいます。
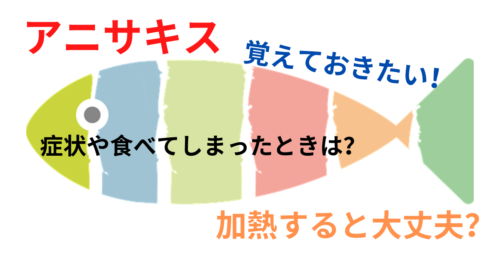
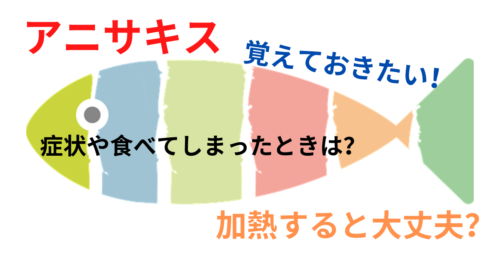
3,アレルギーの心配
離乳食の間は、アレルゲンになりやすい食材は避けているため、その子にアレルギーがあるかどうかは、まだわからない状態です。
お刺身に限らず初めての食材は、慎重に食べさせなければいけません。
アレルギーについては後程詳しくご紹介します。
生卵は?食べさせてもいい?



卵は完全に火を通していれば、離乳食で7か月頃から与えることができます。
しかし、しっかりと火を通したとしても、卵は強いアレルギー反応を起こす可能性のある食材ですので、注意深く赤ちゃんの様子を見ながら少量ずつ与えていかなければいけません。
アレルギーの次に心配な食中毒に関しては、火を通さない卵の方がはるかに危険です。
小さな赤ちゃんの場合、最悪の場合は命にかかわるほど重症になる可能性があるので早くても3歳を過ぎてから与えるようにしましょう。
卵に多い食中毒は、主に”サルモネラ菌”によるものです。
生に限らず、調理の際には細心の注意を払うようにしなければいけません。
卵の調理に関して守らなければいけないことは、次の通りです。
- なるべく新鮮なものをえらぶ
- 卵の殻にひびが入っているものは使わない
- 卵を割ってからは素早く調理するか、食べる
- 卵の殻を触った手、触れた調理器具は調理後の食材や口などに触れないように十分気を付ける
特に3歳を過ぎたお子さんに与える場合でも、上記のことを守って安全には細心の注意を払いましょう。
さらに、体調が悪い時には生卵はをさけ必ず完全に火を通して与えるようにしてください。(できれば卵は与えない方が無難です)
生物と食中毒の関係



食中毒に関しては、ニュースや身近な人などの話などで知っている人も多いかとは思います。
怖いものだと認識していても、なんとなく特別なことのような気がしている人も多いのではないでしょうか。
しかし、実は食中毒を起こす細菌はごく身近なところにたくさん存在します。
そして、大人の人が大丈夫でも乳幼児やお年寄りなどは、ごくわずかな細菌でさえ食中毒につながる可能性が高いということを覚えておいてください。
赤ちゃんに関しては、体がまだ未熟な上に、抵抗力はもちろん免疫力も未熟であるため、その危険性はさらに高くなってしまいます。



多くの細菌は、加熱することで死滅しますが中にはそうでないものも存在します。
さらに、多くの細菌は決まった条件下であれば短時間でどんどん増えてしまいます。
例えば、お刺身を食卓に並べて長い時間食事をする場合、食べている間にも細菌は増え続けてしまいます。
生卵に関しても同じように、時間が経てばたつほど細菌は増え続けます。
そのため、赤ちゃんに生ものを与える場合は、なるべく常温で放置する時間が短いうちに与えるようにしましょう。
特に注意していただきたいのが、お刺身の場合は回転寿司です。
レーンを回っているお寿司の場合、どのくらいの時間常温にさらされているかわからないので避けましょう。



1回ずつ注文をして、早めに食べきるようにしましょう。
そして、生卵の場合はすき焼きなど温かいご飯やお肉などに触れることで、温度が上がってしまうので細菌の繁殖も早いので、早めに切り上げるか時間が経ってしまったものは与えないように気を付けてください。
赤ちゃんが成長するにつれて、免疫力や抵抗力、さらに消化機能なども成長しますので、ママやパパは大変かもしれませんが、お子さんが小さいうちはオーバーなくらい注意してあげてください。
実はとっても危険なアレルギー!慎重にならなければいけない理由と食材
食中毒と同じように気を付けなければいけないのが【アレルギー】です。
特に、近い身内にアレルギー体質の人がいる場合は、新しい食材を与える際に十分注意しなければなりません。
卵や甲殻類、ナッツや青魚などアレルギーの原因となる食材はたくさんありますが、生ものや生卵を初めて与える時は慎重に様子を見ながら与えましょう。
万が一に備えて、初めての食材に挑戦する際は病院にすぐ行けるように、平日の午前中がおすすめです。
お刺身の場合は、あじやサバなどの青魚はほんの少量からはじめて、徐々に増やしていくようにしましょう。
さらに、火を通しているときにはアレルギー反応がなくても、生ものの場合はアレルギーを起こすということも考えられます。
お刺身は3歳すぎから与えてもいいとなっていますが、アレルギーのことを考えると、無理に始めることはお勧めできません。
ゆっくりと、お子さんの様子や体質を見ながら慎重に始めるようにしましょう。
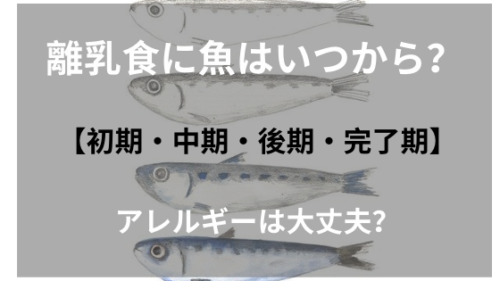
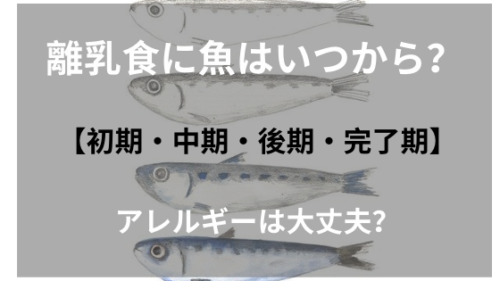
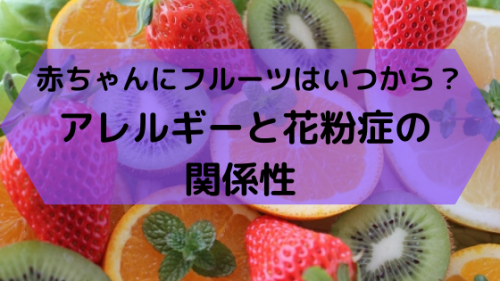
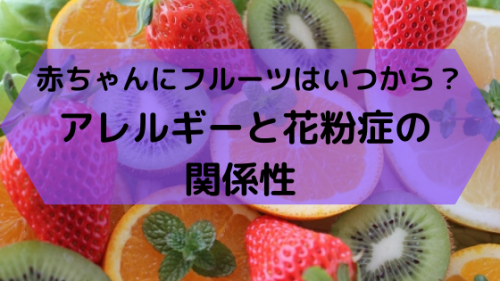
赤ちゃんと一緒に安全に食事をするために大切なこと
お刺身や生卵、さらにはいくらや貝類など美味しいものを早く食べさせてあげたいという、親の気持ちはよくわかります。
しかし、体が未熟な赤ちゃんにとって、時には毒となる場合もあることを認識して【年齢・体調・体質】などを考慮してパパやママも我慢が必要になります。
食べられる年齢になったとしても、必ず次のことに気を付けるようにしましょう。