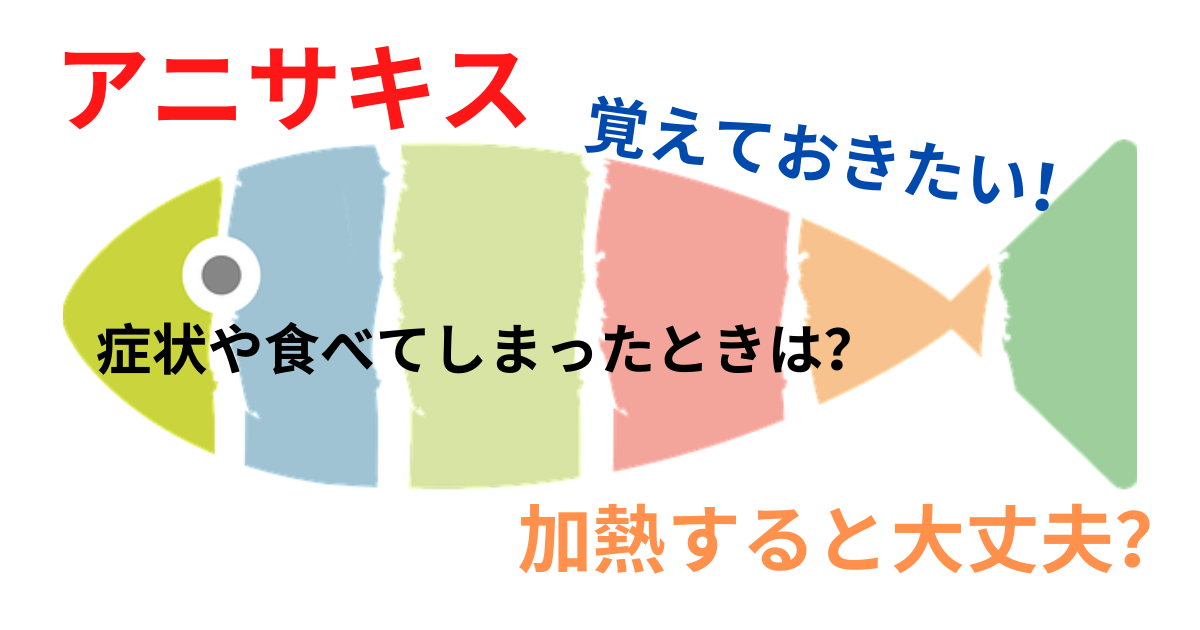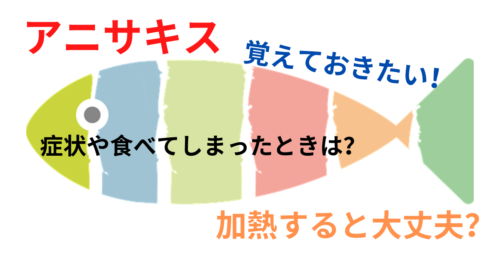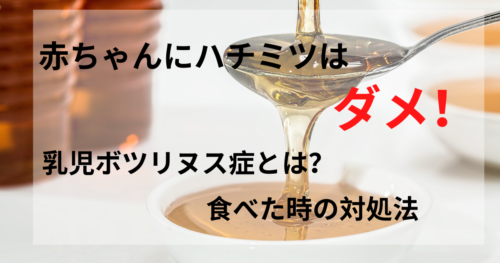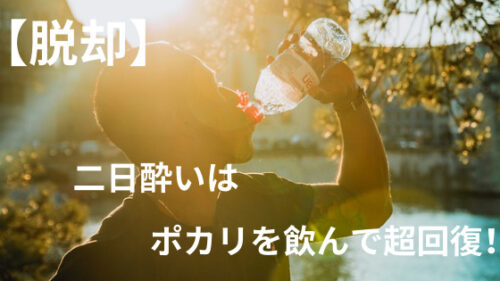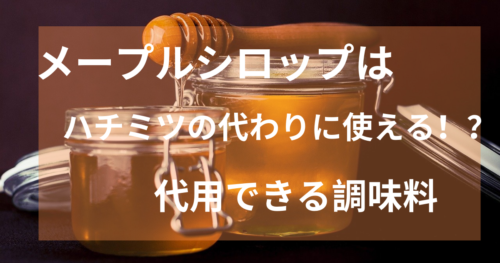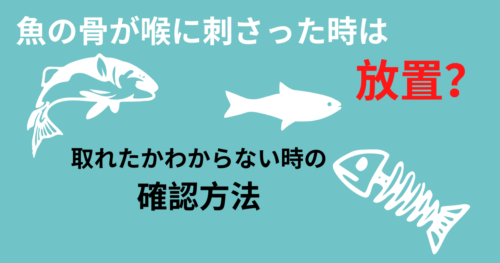龍之介
龍之介アニサキスという寄生虫をご存知ですか?
近年ではニュースでも取り上げられたりと、話題になっていたこともありましたが、アニサキスとは一体どのような寄生虫なのでしょうか?
ということで今回はアニサキスについての記事となっています。
アニサキスとは?
アニサキスとはアニサキス亜科に属する線虫の総称で、イルカやクジラなどの海生哺乳類や魚介類に寄生する寄生虫です。
このアニサキスの第三期幼虫が寄生した魚類を人が経口摂取することで、「アニサキス症」を引き起こす原因となります。
アニサキス症とは?



アニサキス症とは食中毒の1つ。
アニサキスが寄生した魚介類を食べることで発症しサバが最も多く、その他にもアジやイワシ、サンマやイカなどからの感染もみられます。
アニサキス症の症状
アニサキス症の症状はアニサキスが寄生した人体の部位によって異なりますが、大半が胃を寄生部位とする「胃アニサキス症」です。
次に腸アニサキス症が多く報告されています。
胃アニサキス症
胃にアニサキス幼虫が刺入することで発症します。
感染源となる魚介類を摂取後、数時間~十数時間後に急激な上腹部痛や悪心、嘔吐を生じます。
腸アニサキス症
アニサキス幼虫が胃を通り越して、腸に刺入することで発症します。
感染源となる魚介類を摂取後、十数時間~数日後に激しい腹痛を引き起こします。
腸閉塞を併発させることもあります。
その他の症状
上記の症状はアニサキス幼虫が刺入することで発症するものですが、アニサキス幼虫が刺入しない場合にも、アニサキス自体が抗原となってアレルギー症状を引き起こす場合があります。
アニサキス症の治療法
- 胃アニサキス症の場合
-
胃内視鏡で虫体を確認し、摘出することで治療することができます。
- 腸アニサキス症の場合
-
症状が治まるまで待つことになるのですが、腸閉塞等を併発していた場合には手術しなければならないこともあります。
アニサキス症は自然治癒はできない。
基本的には胃カメラで虫体を除去するのですが、困難な場合は体内の中でアニサキスが死ぬのを待つ場合もあります。
アニサキスは人間の体内では生きられないので早くて1~2日遅くても3~4日で死滅するからです。
ただこれは、点滴など病院で何かしらの処置をして死滅するのを待つということなので、自己判断での自然治癒は絶対にダメです。



とは言ってもアニサキス症の痛みは、のたうち回るほどの激痛なので我慢できないと思いますが・・・。



アニサキス症の疑いがある場合、早急に病院へ行きましょう。
アニサキス症の予防対策
アニサキスが寄生している魚介類は食べることができないのか?と思うかもしれませんがそうではありません。
寄生していても、ちゃんと処理すれば食べることができ、アニサキス症にもなりません。
アニサキス症を予防するには【鮮度と目視】さらに【加熱・冷凍処理】が有効になります。
鮮度に注意する


アニサキス幼虫は通常内臓に寄生しています。
しかし、寄生している宿主が死ぬと筋肉(身)へと移動することが知られています。
魚を丸ごと1匹購入した際は新鮮な内に速やかに内臓を取り除く必要があります。
そして当然ですが内臓を生で食べないでください。
目視で確認する


アニサキス幼虫は長さが2~3センチほどの白い糸のような形をしています。



目で十分に確認することができるので発見したら取り除いてください。



調理中や刺身を食べるときには確認するクセをつけてみるといいかもしれません。それぐらい目視で確認できます。
アニサキスの加熱・冷凍処理


アニサキス幼虫は高温に弱く、加熱することで処理できます。
70℃以上なら瞬間的に、60℃以上なら1分の加熱でアニサキスが死滅。
低温には強いのですが、-20℃で24時間以上冷凍することでも処理できます。
しかし、家庭用の冷蔵庫は-18℃が多いので倍の48時間以上の冷凍を目安にしましょう。
これらは厚生労働省が予防方法として挙げている方法です。
間違った予防法。
食酢・塩漬け・醤油やわさび漬けなどしてもアニサキスは死滅しません。
よってシメサバや塩辛でもアニサキスの可能性があるということを頭に入れておきましょうね。
よく噛んで予防することもできる。



あまりしたくはありませんが・・・
うっかりアニサキスを食べてしまってもよく噛むことでアニサキス症を防ぐことができます。
アニサキスは刺激に弱い特徴もあり傷つくと死んでしまうからです。
アニサキス症になるのは体内の中でアニサキスが生きているからで、死んでしまえば食べても問題ありません。
そのため、刺身で食べる場合も細かく切ったり飾り包丁を入れるのも効果的なんですね。



特にイカなら細かく切って、いかそうめんにするのがいいですよ。
ちなみにアニサキス自体に毒性は確認されていません。
アニサキスが多い魚ベスト3
- サバ
- イカ
- サンマ
サバ。





冒頭でもお話ししましたが、サバからの報告例が圧倒的に多いです。
アニサキスは熱に弱いのでサバ?と思うかもしれません。サバを刺身で食べることなんてほとんどありませんよね?
でも、よくよく考えてみてください。
シメサバは生のサバを酢でしめただけで加熱調理してません。
アニサキスは酢漬けでは死滅しないので、シメサバを食べる時は特に注意が必要で【目視・よく噛む】を意識しましょう。
イカ。





サバの次に報告例が多いのがイカ。
その中でもスルメイカが注意です。
特に自家製の塩辛には注意したいところ。上記でも言ったように塩漬けじゃ死滅しませんから。



逆にスーパーなどで売られているイカの塩辛は安心して食べていい現実があります。
それは、スーパーなど企業が生産している塩辛は冷凍原料つまり、冷凍保存したイカを使用しているからなんです。
先ほどお伝えした通りアニサキスは冷凍でも死滅します。



だから自家製の塩辛よりも販売されている塩辛のほうが安全なんですね。
サンマ。


最近では流通状況もよくなってサンマの刺身をちらほら見かけるようになりました。
食べたことがある人も多いんじゃないでしょうか。
生姜醬油につけて食べるとサンマ独特の甘みが広がって美味しいんですよね。
しかし、これが逆にサンマ経由のアニサキス症の増加を招いてしまったんです。



しかも注意したい魚介類ベスト3に君臨する始末。(苦笑)
すべての魚に寄生しているわけではない。



アニサキスが寄生しやすい魚とそうではない魚がいます。
ほとんど寄生していない魚は養殖魚。
魚が普段食べるエサや量によって寄生のしやすさが変わってきます。
養殖魚はしっかりと管理された場所で人工ペレットと呼ばれているエサを与えられているのでアニサキスの危険がほとんどないのです。
また、刺身で食べるとするなら魚屋さんが刺身用として販売しているものなら安心しても良いかもしれません。
最近でこそアニサキス症が話題となっていますが、アニサキス症は昔からあります。



つまり魚屋さん=プロの方は昔からアニサキスのことを熟知されているので、安心できるといったところです。