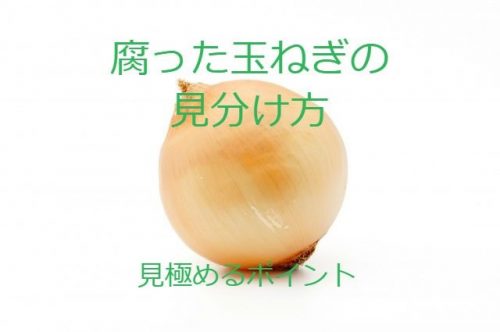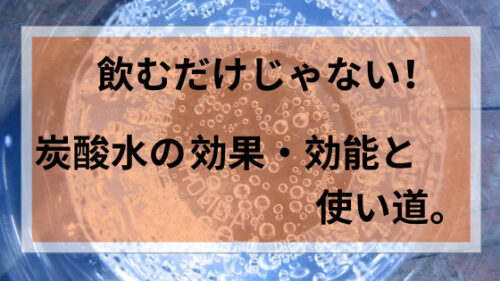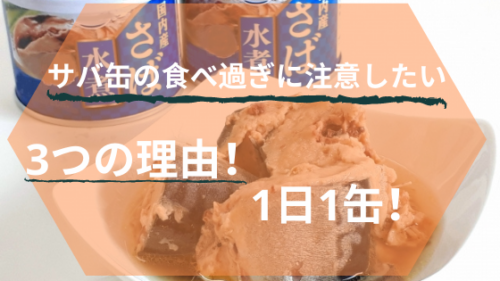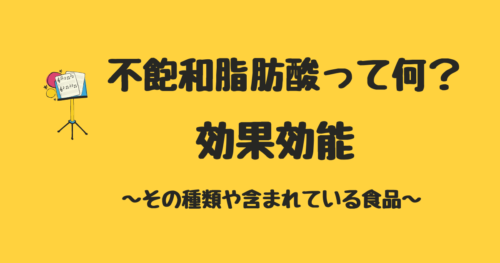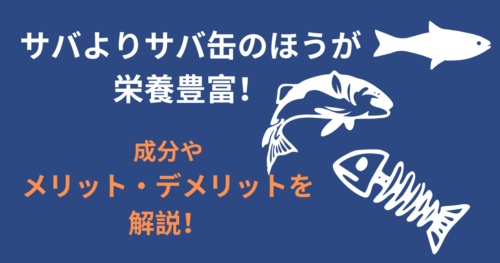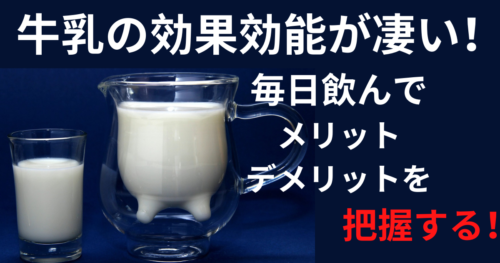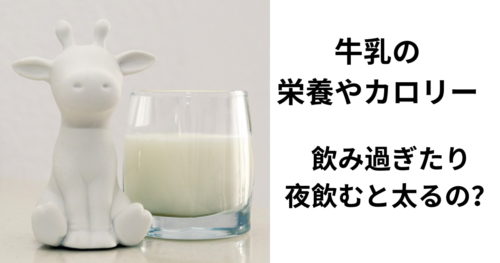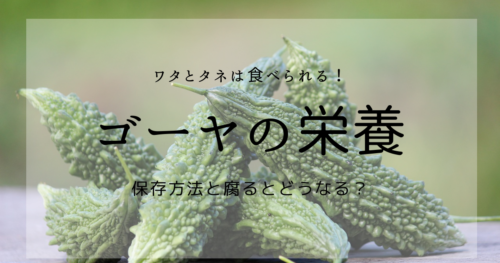亜鉛という栄養素を聞いたことがあるとは思いますが、どのような効果効能があるのはご存知ない方も多いはず。
今回はそんな”亜鉛”について【7つの効果効能・亜鉛不足になると?・亜鉛を含む食材】などなど亜鉛についてお話ししていきたいと思います。
亜鉛とは?
亜鉛は必須ミネラルの中の1つで体内では作りだすことができないので、食べ物やサプリメントから摂取する必要があり身体の中に貯蔵場所がないので毎日の食事からとるのが基本です。
成人の体内に約2g含まれていて、そのほとんどは筋肉と骨中に含まれていますが「皮膚・肝臓・膵臓・前立腺」など多くの臓器にも存在しています。
そのことから亜鉛がもたらす効果効能は生きていくうえで欠かせない栄養素であり不足していると日常生活に大きな支障を与えてしまうのです。
亜鉛の効果効能。
- 筋力アップ効果
- 味覚の正常化
- 抗酸化作用の活性化
- 免疫力の向上
- 発育、成長
- 美髪、美肌
- 生殖機能の改善
筋肉アップ効果。
筋トレ・運動すると筋細胞が傷ついてしまいます。
傷ついた筋細胞の修復・新陳代謝が進むことによって筋トレ・運動した効果が現れるんですね。
筋トレ・運動している時に体内に十分な亜鉛が貯蔵されていると、この働きがスムーズに進みより効果を実感できます。
筋肉の材料になるのはタンパク質ですが亜鉛も同じぐらい重要なんです。
味覚を正常にする。
舌には味蕾(みらい)という受容器官があり、この部分で味を感じ取ります。
味蕾の細胞は早いペースで生まれ変わる特徴があるのですが、この働きが上手く行われないと味覚に異常出てしまいます。
亜鉛にはこの働きを支える重要な役割があるので欠かさないことが大事。
味蕾の働きを保ち、味覚を正常に保つ効果も亜鉛にはあります。
抗酸化作用の活性化。
亜鉛は体内のビタミンAの代謝を促進する働きがあり抗酸化作用が活性化します。
抗酸化作用が活性化すると生活習慣病予防の効果に期待できほか、過酸化脂肪の害を防ぐのでアンチエイジング効果にも期待できます。
免疫力の向上。
抗酸化作用が活性化するので免疫力の向上効果もあります。
体内のビタミンAをとどめておく効果から粘膜を保護し喉の痛みや鼻水・鼻づまりなどの症状を緩和。
体内に入った病原菌を攻撃する白血球にも亜鉛が含まれていて病気の症状を緩和するだけじゃなく早期回復にも亜鉛が必要になります。
発育・成長に欠かせない。
亜鉛にはタンパク質の代謝を促進する働きがあります。
この働きにより、全身の新陳代謝がより活性化することになります。特に成長期の子供は新陳代謝が活発で、より多くの亜鉛が必要になってくるので不足している状態は好ましくありません。
美髪・美肌効果。
髪の毛や皮膚もタンパク質からできているんですね。
亜鉛はタンパク質の代謝を促進するので亜鉛の働きが重要になります。
とゆうのも髪や肌の代謝サイクルは早くタンパク質だけでは物足りなく悪くなってしまいます。
タンパク質・亜鉛、双方が十分にないと髪なら【毛質・抜け毛】肌なら【肌荒れ】などの悪影響を受けてしまいます。
以上のことから亜鉛には美髪・美肌効果があると言われているんですね。
生殖機能の改善。
 龍之介
龍之介コチラは男性のみのお話しになりますw
男性の前立腺・精子には多くの亜鉛が存在しています。
精子の形成には亜鉛が必要で亜鉛から作られていると言っても過言ではありません。(それほど大事)
また、男性の悩み1位である【抜け毛・髪が薄くなる】といったハゲ予防にも亜鉛は効果的ですので男性の皆さんは亜鉛不足にならないよう気をつけましょうね。
ハゲ予防の余談として亜鉛だけじゃなく青魚の脂である【DHA・EPA】も大変効果的ですので参考にしてみてください。
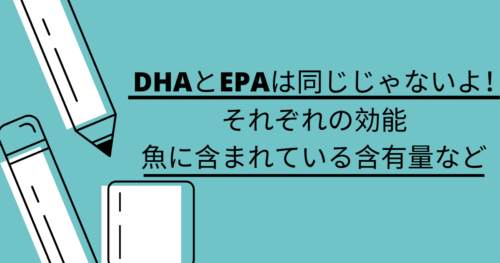
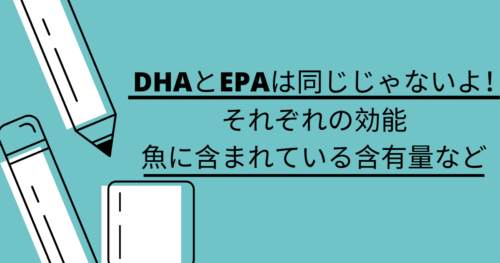
亜鉛を含む食材一覧ランキング。
| 食材 | 100gあたり | 亜鉛含有量(mg) |
| 肉類 | 豚レバー | 6.9 |
| 牛レバー | 3.8 | |
| 鳥レバー | 3.3 | |
| 牛もも肉(生) | 4.4 | |
| 鳥もも肉(皮なし) | 2.0 | |
| 魚介類 | 牡蠣 | 13.2 |
| ほたて(生) | 2.2 | |
| うなぎ | 1.4 | |
| たらこ | 3.1 | |
| 大豆製品 | 納豆 | 1.9 |
| 木綿豆腐 | 0.6 | |
| 高野豆腐 | 5.2 |
亜鉛を含む食材はもっと多くありますが、代表的なものを記載しました。
亜鉛の含有量が1番多いのは牡蠣になります。好き嫌いが多い食べ物ですが亜鉛は身体にとってとても大事な栄養素なので積極的に食べていきたいですよね。
そして食材に含まれている亜鉛の含有量は食べたらそのままの量(mg)が体内に吸収される訳ではありません。
亜鉛の腸管吸収率は約30%前後とされています。



ビタミンCを含む食材と一緒に食べることで吸収率を良く出来るのでレモンなどの柑橘系と合わせてみましょう。



逆に一緒に食べると亜鉛の吸収率を妨げる食材もあります。
- 穀物や豆類に多く含まれる「フィチン酸」
- ほうれん草に多い「シュウ酸」
- 加工食品に多い「リン酸塩、ポリリン酸」



亜鉛の吸収を妨げてしまうので注意が必要です。
1日の亜鉛摂取推薦量
| 性別 | 年齢 | mg/日 |
| 男性 | 15~69歳 | 10mg/日 |
| 70歳以上 | 9mg/日 | |
| 女性 | 15~69歳 | 8mg/日 |
| 70歳以上 | 7mg/日 | |
| 妊婦 | 10mg/日 | |
| 授乳婦 | 11mg/日 |
亜鉛不足と言われている理由。
以外と少ない数値に見えるかもしれませんが国民健康栄養調査(平成25年度版)によると現代人の亜鉛摂取量の平均は男性8.88mg女性7.12mgと推薦量に満たしていない現実があります。
それには亜鉛の吸収率が約30%前後によることや吸収を妨げてしまう栄養素があることも関係していますが、偏った食生活や無理なダイエットによる理由が大半を占めています。
そして「お酒をよく飲む人」「赤ちゃん」「高齢者」の人は亜鉛不足になりやすい傾向があります。
お酒をよく飲む人。
亜鉛はアルコールの代謝を手助けする酵素の材料でアルコールを飲むことで亜鉛を消費します。
それプラス、アルコールは利尿作用もあるので尿中の亜鉛も排出する性質があり亜鉛不足になっている可能性が多いにあるんですね。
赤ちゃん。
赤ちゃんが亜鉛不足=母親が亜鉛不足になっていることが多いんです。
1日の亜鉛摂取推薦量を見てもらえればわかるように、授乳婦の方は1日11mgと多くの亜鉛が必要とされています。
赤ちゃんは母乳の栄養素から亜鉛を摂取しているので母親が亜鉛不足だと赤ちゃんも亜鉛不足の図式が成り立つんですよね。
亜鉛の効果効能には「発育・成長」がありますから不足している状態は避けたいものです。
赤ちゃんが亜鉛不足にならないためにも母親が食生活を気を付け亜鉛を十分に摂取しておくことが大切です。
高齢者。
高齢になると食が細くなり亜鉛の摂取量が必然と少なくなってしまうのが1つの理由。
そしてもう1つが消化機能の低下によるものです。
亜鉛の吸収率は約30%前後ですが消化機能が衰えていると、さらに吸収率が悪くなってしまうのです。
このような2つの理由から高齢者の方々は亜鉛不足の傾向が高いと言える現状があります。
亜鉛はサプリメントでも摂取可能ですので「亜鉛不足が気になる・亜鉛不足の症状が出ている」方はサプリメントがオススメです。
亜鉛不足になると?
- 味覚障害
- 風邪にかかりやすい
- 口内炎
- 食欲不振
- 髪の毛が抜けやすい
- 貧血
- 小児の成長障害
- 肌が乾燥しやすい
- 皮膚炎になりやすい
- 傷の治りが遅い
- 傷、虫刺されが膿んでしまう
- 性欲が落ちた
- 爪に白い斑点んがある



上記の項目に思い当たる箇所があれば亜鉛不足になっている可能性があります。
亜鉛を意識して食生活を変えれば症状が改善されるかもしれません。
また、亜鉛不足の症状を見てもらえるとわかるように亜鉛不足は日常生活に大きな支障を与えてしまうので注意してくださいね。
亜鉛の過剰摂取。
規則正しい食生活なら亜鉛の過剰摂取の心配はありません。むしろ1日の亜鉛摂取推薦量に満たしていない現実もありますから・・・。
ただ、亜鉛のサプリメントを服用している方は過剰摂取による副作用が出る可能性があります。
「悪心・嘔吐・食欲不振・下痢」などの副作用があり1日に亜鉛を食事・サプリメントを含め2g以上摂取した場合に起こります。
サプリメントはあくまでも食事で不足している分を補うためだけにとどめ過剰摂取にならないよう気を付けましょう。